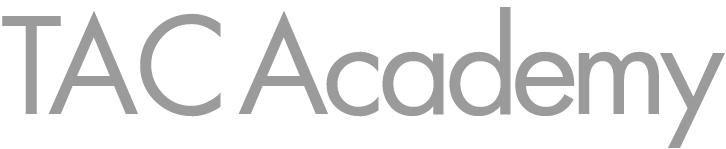こんにちは、幸代です。
9月18日に日本の暑さに耐えられるか戦々恐々としながら帰国しました。
が、なんとラッキーなことに、まさにその日から気温が下がり、ソフトランディングする事が出来ました。
息子と一緒に帰国して、まず最初に食べたい物はうなぎ、青身魚、焼き魚、干物等でした。
実家から車で30分弱、猛暑で有名な岐阜県多治見市があり、そこは私のイチオシのうなぎ店があり早速、食べて来ました!
なぜ多治見でうなぎが有名かというと、美濃焼の窯業で働く職人たちが窯の炎で消耗した体力を回復するために、高タンパクで消化の良いうなぎを日常的に食べていたそうです。
知らなかったのですが、天然うなぎの旬は10月から12月だそうで、でも今は一般的には養殖なので、夏の土用の丑の日に合わせて育てられているため、一年を通じて安定して流通しているそうです。
もう皆さんはご存知のことかもしれませんが、少しうなぎについて調べてみました。
関東のうなぎは江戸時代の武家文化に影響を受けて背開き(切腹のイメージを嫌い)で、一度蒸してから焼くので、ふっくらとして、大きく見えることは「見栄を張る」武家文化では好まれたそうです。
また一度蒸して火を通すことで調理時間が短縮され、せっかちな江戸っ子気質にあったそうです。
日本の中央に位置する尾張名古屋地区の多治見は関西と同じ腹開き、直火焼です。うなぎを生からじっくり焼くため、時間がかかり、表面がサクッ、中がふんわりに焼くには職人の技術が必要だそうです。
関西風と言われる由縁は、商人は腹を割って話す、じっくり商談したいため、うなぎの焼く時間が少しかかるくらいがちょうどよかったとか、商人文化から好まれたとか、うなぎの食文化にそんな違いが色濃く残っているのは面白いですね。
あと、尾張名古屋には「ひつまぶし」と櫃の中にごはんと1センチ幅くらいに刻まれたうなぎが入っていて、1杯目はそのまま、2杯目薬味を加えて、3杯目出汁でお茶漬けに、4杯目最後はお好みの方法で食べるなんていう、うなぎ料理があります。
熱田神宮近くにある創業150年の「あつた蓬莱軒」は「出前で食器を割る回数を減らせるよう、大人数分のうな丼を大きな櫃にまとめていたが、うなぎを平等に分けられず、ごはんばかりが残ってしまったため、うなぎを細く切ってごはんと混ぜたのが始まり」とのこと。
由来は店によって異なるようで、いずれの話にも様々な知恵と工夫が生み出した料理なようです。
とにかく私はパリッと香ばしい地元のうなぎがやはり好きです。
先日、多治見「うな千」で上うな丼を3650円で食べて来ました。安っすい!!!

なぜ超感動したかと申しますと、先日アメリカシカゴ空港で買った、ただの普通のハムサンドイッチ1つが税込21ドルしたからです。側にいた息子が「本当に買うの??」と顔を覗き込んできました。それは@¥150で計算すると3150円でした!
日本の秋は安くて美味しい物ばかり、まだしばらく満喫できそうで、私はとても幸せです!
ではまた来月!